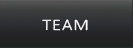![]() 今回は、離婚後の未成年の子どもとの面接交渉権についてのご相談です。
今回は、離婚後の未成年の子どもとの面接交渉権についてのご相談です。
そもそも、面接交渉権とは、未成年の子のいる夫婦が離婚した場合等に、親権者もしくは監護権者でない親が、その未成年の子と面接し交渉する権利をいいます(有斐閣「法律用語辞典第3版」参照)。
![]()
この面接交渉権について、直接的に規定した法律はありませんが、民法766条1項の「監護について必要な事項」、同法同条2項の「監護について相当な処分」、家事審判法9条1項乙類4号及び人事訴訟法32条1項の「子の監護に関する処分」が、面接交渉権の実定法上の根拠になると考えられています。
また、判例上も「親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は未成熟子の福祉を害することがない限り、制限され又は奪われることはない」(東京家庭裁判所昭和39年12月14日審判)と判示されています。
そして、実際の面接交渉の内容(回数、方法等)については、父母の話し合いによって決まれば、何ら問題はありませんが、父母の協議が整わないときは家庭裁判所の調停・審判の手続きを利用することになるのが通常です。
![]()
この家庭裁判所の調停・審判の手続きでは、前述の審判例からも明らかなように、子の福祉の観点から面接交渉の可否及びその具体的内容を判断すべきであり、面接交渉が子の福祉を害すると判断される場合には面接交渉に制限が加えられることになります。
この点、「子の福祉」とは何かが問題となりますが、子の年齢・成育状況・健康状態等に照らして子に与える影響、同居している親の監護養育に与える影響などの諸般の事情を考慮して判断することになります。
ちなみに令和2年の司法統計によると、面接交渉事件に関して調停が成立した事件11,288件のうち、月1回以上の面接というものが4,818件となっており、面接交渉の回数については月に1回程度が多いと言えそうです。